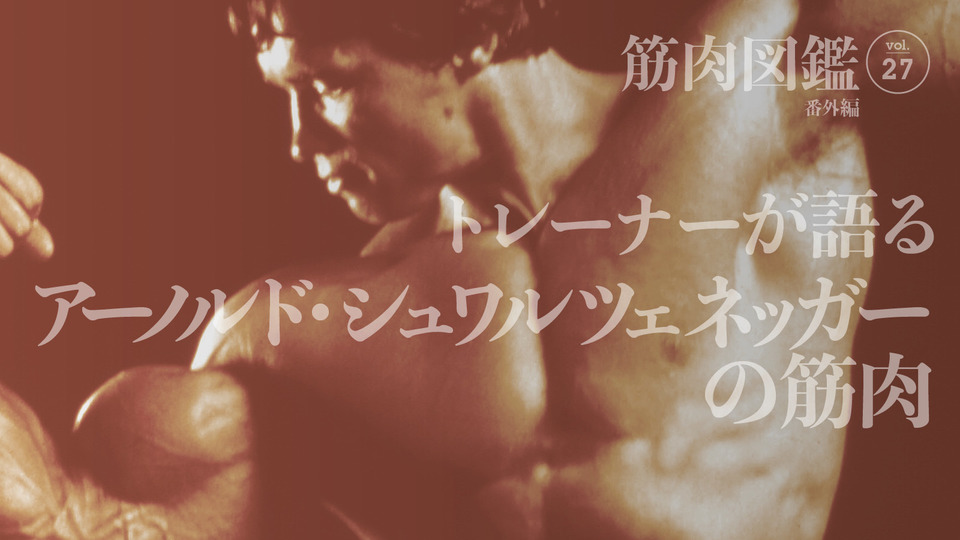「範馬勇次郎の肉体になりたいと願えば、実際にそうなれる」ボディビルダー・横川尚隆
長く継続するほど有利とされるボディビルの頂点に、20代の若者がわずか4年間の鍛錬で上り詰めた!革命的な出来事をどう感じ、次は何を目指す?(雑誌『ターザン』の人気連載「Here Comes Tarzan」、No.792〈2020年7月22日発売号〉より全文掲載)
取材・文/鈴木一朗 撮影/藤尾真琴
(初出『Tarzan』No.792・2020年7月22日発売)

ケガをするような鍛え方に耐えるのも才能。
見てのとおりのイケメンである。テレビにも何度も出演しているので、ご存じの方もいるだろう。日本人ボディビルダーとして一般の人にここまで広く認知された存在は、おそらくこの横川尚隆が初めてであろう。
彼は2019年の日本ボディビル選手権で見事優勝を果たした。この結果は、彼にとっては悲願であり、絶対に成し遂げなくてはならないことでもあった。なぜなら前年、つまり2018年の同大会で日本のボディビル第一人者であり、世界的にも活躍する鈴木雅に惜敗しているからだ。

「悔しかったですね。点数的には僅差でしたし、まわりの人もいい勝負だったと言ってくれた。自分でも勝てなくなかったというか、勝つつもりでいました。それで負けたということは、まだまだボクの努力が足りなかったと単純に思ったんです。鈴木さんはすごく尊敬している選手ですが、大会時は“トップにいるから倒す対象”って感じですね。自分のことが情けなくて次は圧倒的に差をつけて勝とうと考えました」
ひとつ、ボディビルについて記しておこう。この競技は極限まで鍛え上げた肉体の美しさを競う。審査員は、筋肉の大きさ(バルクという)、脂肪の薄さと筋肉のカタチ(それぞれカットとディフィニション)、そしてカラダ全体のバランスを総合的に考慮して点数をつける。
となれば、審査員の心理が微妙に判断を左右する要因となりかねない。もし、優劣つけがたい2人がいたら、何度も日本一に輝いた日本の代表的ボディビルダーに、無意識のうちに得点を傾けることもあるだろう。
だからこそ、横川は圧倒的な肉体を作ろうと決心したのである。もちろん彼は18年の、つまり2位に甘んじた大会に向けても、超絶的なトレーニングを行っていた。それ以上やるというのは、一歩間違えば選手生命を絶たれることを意味していた。

「それまでの倍ぐらいやりました。これは時間ということではなくて、質とか気持ち的にということですが。具体的にはフォーストレップスを取り入れ、限界が来た後もトレーナーさんの補助でさらに挙上するトレーニングを行いました。
3、4回ぐらいしか上がらない重さを、補助付きで10回ぐらいやる。だいたい1種目5セットやります。それを8種目、2時間ぐらいで行います。
1日のトレーニングで鍛えるのは1部位だけ。カラダのダメージはとんでもないですよ(笑)。でも、これでケガしたらそこまでの器だったのかなと思っていました。
トレーナーは武井(郁耶)さんというのですが、絶対的に信頼しています。フォーストレップスも、ただ上げるだけじゃまったく意味がないんです。同じフォームで同じところに効かせないといけない。
もちろんボクの技術も重要なんですが、武井さんもボクの残りのパワーや、上げるときの軌道なんかを見極めながら補助してくれる。だからこそ、限界ギリギリまで鍛えられたし、ボクの補助はあの人にしかできない。感謝しています」
昨年の大会に鈴木雅は出場しなかった。勝負という意味ではちょっと悔しくないですかと聞くと、「たとえ鈴木さんが出場していても、負ける気はありませんでした。それだけの自信があったんです。やれることはすべてやって絶対的なカラダを作り上げた。だからまったく悔しさはないです」と答えた。彼の出現でボディビルの世界は少しずつ変わっていきそうな予感がするのである。
どこを鍛えているか、初めから感じ取っていた。
横川がボディビルを始めたのは4年前。つまり、4年で日本一の肉体を作り上げた。
これは、従来ありえない話だった。カラダはすぐに大きくならないから、通常は競技に出場するレベルに到達するまでに莫大な時間がかかる。初めて東京選手権で優勝した鈴木雅が日本選手権で優勝するために、5か年計画を立てたという事実でも、それはわかる。
「空手やボクシング、それにキックボクシングなど格闘技をずっとやってましたが、その頃から筋肉質だなと思ってました。高校時代に肩や腕はセパレートしてたし(割れ目がつくの意)、全身バキバキでしたから。
当時まったくウェイトトレーニングしてませんでしたが、格闘技をやっているだけでカラダがどんどん大きくなっていく。その感覚が楽しいと思ってはいたんですね」

フィジークという競技がある。これも肉体美を競うのだが、ボディビルほどに大きな筋肉は求められない。もしかしたら、より一般人が憧れる体型といえるかもしれない。
横川はトレーニングを始める前に、ベストフィジークジャパンという大会に出場し、ミスターベストフィジークの2位になった。何もしていなくても、この結果なのである。
「ウェイトトレーニングを始めたのはその後、専門学校に行くようになってからです。漫画『グラップラー刃牙』に出てくる範馬勇次郎の肉体を見て、こうなりたいと思ったのがきっかけでした。
体育系の専門学校に無料で使えるジムがあり、そこで鍛えだした。自己流で始めたのですが、最初から1部位2~3時間かけてやっていました。格闘技だと一日中練習という場合もあるし、こんな短い時間でいいのかなと思ったぐらいです。
腕の日は二頭(上腕二頭筋)と三頭(上腕三頭筋)だけ鍛えます。知っているメニューをすべてやる。マシンだったり、フリーウェイトだったり、ケーブルだったり。たとえば、三頭だったらフレンチプレスを両腕でやり、片腕でやり、ケーブルのアタッチメントを替えて効かせる。
効くところが微妙に違いますから。その頃は三頭のどのポイントに効くという知識はないんですが、それぞれ筋肉のどのあたりを鍛えているか感覚的にはわかった。もしかしたら、これがボクの才能といえば才能だったかもしれません」
そして半年後、オールジャパンメンズフィジークに出場。172cm以下級で優勝するのである。このとき横川は「自分がしっかりと戦える場所を見つけた」と思った。と同時にフィジークという競技に飽き足らなさを感じるようになっていた。

「優勝しても、自分が思っていたのと違うという感覚があったんです。フィジークでは1位でも、カラダを比較して見ればボディビルのほうが断然すごい。競技が違うので2つを比較するのは間違っているのですが、自分よりすごい肉体の人がいることが気に食わなかった。だったら、ボクがボディビルで日本一になればいいんだと思ったんです」
フィジークでは全体のボディバランスが重要視され、筋肉を肥大させすぎるとマイナスポイントになることが多々ある。だが横川には「とにかく大きくしたい」という渇望に近い切実な思いがあり、誰が見ても最高のカラダになりたかった。ボディビルという競技は、そんな横川のためにあるような競技だった。
「トレーニングに対する感受性も高かったし、筋肉の付き方もボディビルに適してました。大きいだけでは勝てないんです。ウェストがギュッと締まって、脚がボンッと広がってというようなバランスや、加えて言えば骨格とかもボディビルに向いていた。そのことに自分で気づくことができた。サッカーとか野球でも、数年ですごく上手くなる人っているじゃないですか。そのボディビル版がボクだと考えています」
普段食べているものには、食事という感覚はない。
ボディビルダーには鍛える以外に、もうひとつ重大な課題がある。それが食事だ。筋肉を大きくするためにはタンパク質を代表とする栄養を十二分に摂っておかないといけないが、といって余分な脂肪を摂りすぎると、筋肉のメリハリが出なくなってしまう。もちろん、大会前には減量するのだが、それ以外の時期の食事も大切なのである。

「メニューは毎日同じです。朝は卵とごはん。昼はトレーニングの前に牛肉とごはん、夕食は鶏の胸肉とごはんです。その他に、間食として1日3回、プロテインとごはんを摂っています。食事という感覚はもうないですね。外食がしたくなったら、たまにですがお店に行って牛丼なんかも食べますけど」
今年は新型コロナウイルスの影響でジムが閉鎖され、ボディビルダーにとって辛い日々が続いた。横川も最大40kgまで設定できるダンベルを買い、家でトレーニングを行った。
「筋肉量は多少減ったけど、いい休みになった」と、彼は笑う。19年に優勝するためのトレーニングは、ケガをしても痛み止めを飲んで続けたというから、回復のためにはちょうどよかったかもしれない。

彼はこの先のボディビル人生を、どう考えているのだろう。この競技は選手生命が長いのだ。
「プロボディビルダーになったので、日本の大会には出場できません。アマチュアしか出場資格がないんです。国内での連覇は考えませんでした。
最近、メディアに出させてもらって、ボディビルや筋トレに関心がなくてもボクを認識してくれる人が増えたことを実感しています。フィジークは一部の若者の間で盛り上がりつつありますが、まだまだ一般に浸透しているとは言いがたい。ましてボディビルはほんの少数の人々のマイナーな世界です。
だから、今後のボクの活動を通して、ボディビルを競技として楽しんで見てくれる人が増えたらと思っています」